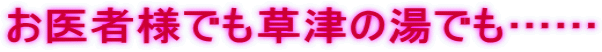「……どうして、あんな事……」
今にも泣きそうな瞳が、それでも弱みを見せまいとするように俺を見つめ、返答を求めている。だけど、俺はそれに応える事は出来ない。なぜなら……。
押し黙る俺に痺れを切らしたのか、一瞬目を伏せ、しかし次には迷いを振り払うかのようにあいつは俺を見据えた。
「答えて、くれないんですね。……俺、先輩と一緒にいるの、楽しかった。昂先輩の前でなら、俺はほんとの俺でっ――」
自分の唇から紡ぎ出された言葉にはっとして、ぶるぶると頭を振ると、あいつはぎっと俺を睨んだ。
「俺……、あんたの事、見損ないました」
決然と、そう言い放つ。
ああ、やっぱりそうか……。
「もう、俺に構わないでください」
裏切られた、と。傷ついた、と。そんな瞳で俺を睨むあいつは、まるで捨てられた小さな子供のようだ。意外と頑固で意地っ張りな性格や、時折見せてくれた本当の笑顔も、もう俺に見せてはくれなくなるんだな。
「……なんとか言ってくださいっ!!」
沈黙を守る俺に最後通牒をつきつけるように声を荒らげるあいつに、俺は口の端で微笑み頭を下げるのがやっとだった。
「……すまなかった」
それしか答えない俺を、あいつは軽蔑しただろう。でも、それでいいんだ。時が経てば、青春の苦い思い出の一つになる。小さな棘のように、あいつの記憶の片隅に残るけれど。
「……さよなら、昂先輩」
そう言ってあいつは俺に背を向け、俺の前から去って行った。
――和仁。俺の邪な気持ちすら、お前は本能的に見抜いていたのかもしれないな……。
その、案外華奢な背中に手を伸ばしたかったけれど。抱きしめて、全てを吐露して、楽になってしまいたかったけれど。俺を『昂先輩』と呼ぶ存在は、後にも先にもお前一人だったのに……。
――ピピピピ、ピピピピ――
耳に障る甲高い電子音。目を閉じたままでも手を伸ばせば届く位置に置いた時計。無意識でそれを止め、むくりとベッドに起き上がる。午前7時。いつもとなんら変わりのない日常。一つ違う所があるとすれば……。
「ちっ。寝覚めが悪いな……」
そう呟いて煙草に火をつけた。ラッキー・ストライク。あいつに「あんた、それ以上の幸運を望むんすか?」なんて毒づかれたが、俺にとっての『幸運』は……。
「ったく、可愛げがないったらありゃしねぇな」
昨晩もベッドを共にしたはずの部下は、「泊まっていけ」という俺の言葉を無視して始発で帰って行きやがった。
あいつ、神崎和仁が俺の会社に転職して来たのは半年前。元々飲食の経験もあり、営業としての手腕もなかなかのもので、社長が惚れ込んで取引先からスカウトしたらしい。なんの因果か、営業企画部に配属され俺の直属の部下になるとは……。
無意識で吐き出したのは紫煙か、それともため息か。
仕事上、部下としての神崎はなんら問題がない。優秀な部下だ。難点があるとすれば。
「ったく、あの毒舌はなんとかなんねぇのか……」
他の社員がいる前ではきちんと敬語を使い、態度も模範的な上司に対するそれではあるが、衆目がなくなった時点であいつは豹変する。本来の姿に戻る、といった方が正しいのか。直属の上司である俺を『あんた』呼ばわりし、そっけない態度で悪態をつく。まあ、意地っ張りな所は10年経っても変わってはいないな。その甘いマスクに張りついた営業スマイルと、華奢な背中に背負った猫はかなりグレードアップしていて、そこは成長したというべきなのかどうなのか。
「まったく、なんでまた会っちまったんだか……」
今までの俺は、来る者は拒まず、去る者は追わず。男女問わず、誘いは断らず。ほとんどが一夜だけの情事や、遊びと割り切ったつきあい、本気になられたらうっとおしくて別れる、そんな関係を続けてきた。
でも俺の前にあいつが現れてから、そんな不毛な恋愛――恋愛とも呼べるものだったのかすらわからないが――を続けているのが馬鹿らしくなってきた自分がいた。快楽に溺れるだけの心のないセックスがつまらなくなった。今までずっとそうしてきたのに。そんな相手じゃもう何されても勃ちもしねぇくせして、あいつの事考えるだけで抜けるなんて、俺は中学生かってぇの……。
酔った勢いもあって、いや酔った勢いでもなければあいつを抱けなかっただろう。あの時のように拒絶されるのが目に見えていたし、しかも今の立場は上司と部下。そして男同士……。あいつが俺を受け入れるはずはないのはわかっていた。だから、あいつから言わせれば『卑怯な手段』に出てしまった。まあ、一度寝てしまえば、俺に傾倒させる自信はあったのは事実だが。
はあ、と長く息と煙を吐き出す。自分でも今のはため息だとわかって苦笑せざるを得ない。
今更ながら、高校時代から俺はあいつに惚れてたんだな、と再確認する。裏表のあり過ぎる一筋縄ではいかない性格も。時折見せた不安そうな瞳、そして屈託のない笑顔も。キャンキャン威勢よく吠える、でも見てくれは可愛らしい柴犬みたいで、放っておけない。吠えられても噛まれてもいいから、かまいたくなってくる。そして、自分だけに尻尾を振ってくれるように仕向けたい。
「……我ながら、結構重症だな……」
俺はラッキー・ストライクを揉み消すと、バスルームへと向かった。
|
|
|