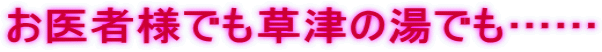「神様って、所詮不公平ですよね」
「は? いきなりどうした?」
ため息混じりの俺の唐突な言葉に、隣にいる課長は一瞬だけ眉を寄せた。男の俺から見ても、素直にかっこいいと思える整った顔立ち。意志の強さを主張するりりしい眉と吊り気味の目元、通った鼻筋、薄い唇、全体的にシャープな印象を与える180近い長身の文句ない色男だ。仕事においてもソツも隙もなく万事完璧、他の社員や社外の人間からも一目置かれた存在だ。
汗で額にはりついた前髪をかきあげ、煙草に火をつける仕草は、やけに色っぽいフェロモンを垂れ流している。――とはいえ、それは『事後』だから当然といえば当然なのだが。
「……はぁ、やだやだ」
「だから何だっていうんだ?」
「いえ、別に。てか、俺にも下さい、課長」
下さい、と言っておきながら、俺は半ば強引に課長の指から煙草を奪う。ラッキーストライク。これ以上の幸運を、それもど真ん中に欲しがるってのか、この人は。なんだか無性に腹が立って、俺は苦い顔でそれをくわえた。
「……課長はやめろ、って何度言わせりゃわかるんだ? か・ず・ひ・と」
「課長を課長と呼んで何が悪いんすか?」
わざと俺を下の名前で呼んだ課長の言葉を完全にスルーし、俺は仰向けに寝返りをうつと紫煙を吐き出した。
「……ちっ。俺のベッドに灰落とすなよ」
「へいへい。課長の買ったばかりのウオーターベッドに穴開けた日にゃ、俺の2ヶ月分の給料がぶっ飛びますからね」
俺が、この人・高瀬昂とそういう関係になってから、まもなく2回目の給料日を迎えようとしていた。
俺が今の会社『ベータフーズ株式会社』に転職してきたのは、半年前の事。うちの会社は都内を中心に飲食店を10店舗ほど経営・フランチャイズ展開している。俺が所属するのは、社内では『事務所組』と呼ばれる営業企画部である。主な仕事は、取引業者との交渉はもちろん、食材の調達、キャンペーンの企画・広報だけでなく、店舗の機器が壊れれば修理を手配し、果ては各店舗の伝票整理や月末棚卸しの手伝いなどなど。まあ、つまりはていのいい『何でもやる課』のような部署だ。
デスクワーク中心のいわゆる『事務所組』は意外と少ない。経理部に4名と、俺達営業企画部に5名、管理部に3名。あとは常務と専務。実は社長が一番の行動派で、社長室のデスクに座って判を押しているタイプではない。空いた時間があれば自分で車を出して各店舗を回ったりしている。『現場組』は各店舗の店長や社員達20数名。そして、事務所・現場どちらにも属さない商品開発部6名は、冗談半分で自分達を『イレギュラー』と呼んでいるらしい。総社員数40名程の企業だが、アルバイト従業員数は200名を越える。
営業企画部……とはいえ部長はいない。現在のメンバーは高瀬課長を筆頭に、千田主任、佐藤尋さん、佐藤ゆかりちゃん、俺の5人。年でいえばゆかりちゃんが一番下だが、短大卒で入社したので俺より社歴は長い、つまりは俺が一番ペーペーって訳だ。
こんな狭い世界で、よもや自分がこんな泥沼のような状態に陥ろうとは夢にも思わなかった。友人達も少しずつではあるが身を固めているし、俺自身もついこの間28歳になった。とはいえ、俺はまだまだ落ち着きたいとは思ってない。どうせなら店舗のかわいい女性社員との合コンや、ちょっと年上のお姉様店長とのラブアフェアーもしてみたいし、そうするもんだと思っていた。しかし、今ベッドの横にいるのは、紛れもなく男で、しかも悔しいぐらいの男前。そして、あろう事か俺の直属の上司だ。
「……はぁ〜」
本日何度目かのため息を紫煙とともに吐き出すと、高瀬課長は俺の左耳を引っ張った。
「――ってえなぁ。何するんすか?」
「さっきからなんだ、ため息ばっかりつきやがって。俺のテクに不満でもあんのか? あんなにイイ声で啼いてよがってたのは誰だ? あぁ?」
その整った顔立ちからは想像もつかないような上から目線の言葉が紡がれるのにも、もうすっかり慣れてしまった。仕事場でも、もちろんベッドの上でも。会社の女性陣は、皆この人を『黙ってればいい男』と口をそろえて言うが、俺も同感だ。俳優やモデルでもおかしくない衆目を集める美貌の持ち主なのに、口から生まれたようなこの人が黙るというシーンを俺は拝んだ事がない。しかも、強気で強引で傲慢で俺様で、この俺なんかが勝てる訳がない……。
「はいはい、あんたにつっこまれてあんあん言ってたのはこの俺ですよ」
半ばヤケでそう答えると、高瀬課長は「ムードもへったくれもないヤツだな」と苦い顔で吐き捨てた。「何がムードだ、ふざけんな、このエロオヤジ!」と出かかった言葉を飲み込んで、俺はベッドサイドの灰皿に手を伸ばし煙草を揉み消した。ま、年は一つしか違わないから、オヤジは言いすぎか。
「……帰ります」
「もう終電ねぇぞ」
「……時間潰して始発で帰ります」
「泊まってけばいいじゃねぇか」
「嫌ですよ。昨日と同じよれよれのシャツとネクタイで出勤なんて、朝帰りがバレバレじゃないですか」
「俺のシャツ着て行けよ」
「何言ってんすか、あんたアホじゃないすか?」
俺の言葉も、この人にとっては子犬がキャンキャン吠えている程度だろう。それでもつい口から出てしまう暴言は、俺のわずかに残ったプライドだ。自嘲するように鼻から息を吐くと、俺はベッドから起き上がった。揺れるウオーターベッドの感触がやけにカンに触る。
「俺とあんた、何センチ違うと思ってんですか? 彼氏のダボダボのシャツ着て喜ぶ女子じゃあるまいし」
「喜ばねぇの?」
俺の言葉を受けてそう返す課長。カチンときて振り返ると、にやりと笑う色男。その顔がますます頭にくる。俺はとっさに枕をつかむと、課長のその整った顔めがけて投げつけた。
「――っ、神崎っ!」
「シャワー借ります」
俺は俺の身体に伸びてくる課長の手を振り払い、さっさとバスルームへ向かった。
まったく、俺は一体何をしているんだろう……自分でもつくづくそう思う。勢いよくシャワーのコックをひねり、まだ冷たい水を頭から浴びた。だるい下半身とうつろな意識が少しだけ覚醒して、俺は念入りに身体を洗いはじめた。
俺が望んでいたのはそれなりの恋愛遍歴とフツーの結婚で。30ぐらいで年下のかわいい嫁さんをもらい、ラブラブな新婚生活、そしてかわいい子供を授かって……。そんなちょっとした夢が音を立てて崩れたのは2ヶ月前、会社の飲み会の後だった。
事務所組の飲み会は、いつも一次会では終わらない。しかもその日は金曜日。飲食業ではあるが、基本的に事務所組は土日休みだ。二次会、三次会となり、1人減り2人減り、気がついたらみんなつぶれていて、まともなのは俺と課長だけだった。その後、成り行きで課長の家に行ってしまったのが失敗だった。
周りに他の人がいた時はいつも以上に饒舌だった課長が、2人きりになってからはやけに淡々と飲んでいた。グラスの中の氷を見つめる目つきがすごく色っぽくて、ちょっとクラッとしたのは否定はしないが、だがしかし俺はいたってノーマルだし、女の子が好きだ。やわらかくて、ふわふわな女の子が。
「なぁ、神崎ぃ・・・」
酔いが回ったせいか、少しだけ呂律が回っていない課長が俺を真っ直ぐ見つめてきた。視線を合わせたら外せなくなると頭のどこかでわかっていて、それでも視線をまともに返してしまった俺も、かなり酔っていたとは思う。
「……やっぱりお前、変わってない。かわいいな」
「――は?」
「ずっと、気になってたんだ、お前の事……高校時代あんな事があったし」
一番触れられたくない部分に触れられ、俺は身構えた。俺と課長は高校時代、同じ部活動の先輩後輩だった。仲がよくつるんでいた時期もあったが、ある日を境に俺達は一言も口をきかなくなった。10年以上も経って、転職先で再会するとは夢にも思わなかったが、お互いに社会人としてある程度の年月も経っていたし、あえてそれに触れずにそれまで過ごしてきた。課長自身も俺がそれが触れられたくない事だとわかっていただろう。だから今まで黙っていたのだろう。なのに、酔いが回っているとはいえ、今になってあの時の事を持ち出すなんて。俺は頭が真っ白になって立ち上がろうとした。
「神崎っ!」
しかし、それより早く、課長は俺の腕をつかんで真正面から俺を見つめた。
「……忘れようと思ったんだ。実際忘れてた、つもりだった……。だけど、お前にまた会っちまった……神崎……」
視線を外さなければ、そう思っていてもなぜかそうする事が出来ない俺に、課長は真顔でつぶやいた。
「やっぱり忘れられねぇわ。お前のほんとは気の強いとこも、口の悪いとこも、それを完璧にカバーする営業スマイルも。……なぁ……」
ただならぬ雰囲気に思わず逃げ腰になった俺の腰をしっかりとつかまえて、その少しだけ潤んだ黒い瞳が、熱にうかされたような瞳が俺だけを見つめていた。
「俺と寝てみねぇか」
そう言って、まるで獣が獲物を襲うようにあっけなく、俺は高瀬課長に喰われた。抵抗しようとしても酔いのせいかうまく力が入らない上、俺より10センチ近く背が高く鍛えぬかれたあの人はびくともしなかった。唇をふさがれ、口内を舌で蹂躙され、強引にベッドに連れて行かれ、まず口で抜かれてイッた俺もどうかしてた。まあ、ちょっと溜まってたのも事実だし、それ以上に課長の愛撫がめまいがするぐらい巧みすぎた。俺はその後、今までの女にもさせた事もないような痴態をさらし、自分自身で聞いた事もないような嬌声をあげ、いきり立ったあの人を奥まで受け入れて、そして泣きながらイッた。
もちろん俺はノーマルだから、男との経験なんてある訳ない。絶対ありえないと思ってた。男につっこむのも、当然俺がつっこまれるのも。だから、あの時の涙は、俺のズタズタにされたプライドだったのかもしれない。酔っていたとはいえ、上司に組み伏せられ、さんざん弄られ、よがってイッてぶっ壊された俺のプライド。一度剥がれ落ちたものは戻らない。あとはもう済し崩し的に、俺達は何度も寝た。酒が入っていてもいなくても。課長の卑猥な攻め言葉と巧みなテクに、俺はいつも乱れ喘ぎまくって、そしていつも後悔する。あの人から与えられるのは、今まで女とのセックスでは味わった事のない享楽的なそれ。こういうのを身体の相性がいい、というんだろうか。頭の芯から爪先まで痺れるような激しい快感と、しかし行為の後には必ず激しい虚脱感が襲ってくる。肉体的なものより、精神的なものの方がはるかに大きい。
あの人の愛撫はやけにねちっこくて激しくて、でも時々愛しい女にするみたいにすごく大切に大切に俺を抱く。めちゃくちゃに攻めて喘がせたかと思うと、やさしく髪を撫でて、俺の頬に唇を落とす。それが、何より俺を惑わせる。あの人の真意がわからない。とはいえ、追求する気もないが。
そうして、週に1.2度、俺は課長と情事を重ねていた。
「はぁ……」
身体と髪を洗い、泡を洗い流して、俺は無意識で盛大なため息をついた。
「何度目だ?」
不意に声がして振り返ると、素っ裸の課長が仁王立ちしている。ついでに下も仁王立ち。
「ちっ」
わざと聞こえるように舌打ちすると、課長がニヤリと笑った。バスルームの鍵をかけ忘れていたのは不覚だった。というか、風呂に入るのに鍵をかける習慣は俺にはない。
「始発まで時間潰すんだろ?」
「誰もあんたと、とは言ってないですよ」
俺の反論も意に介さず、課長は人の悪い笑みで俺を壁に追いつめる。密着する肌、俺の腹にガッチガチのモノが当たっていて、かなりげんなりする。
「あんた、マジでなんなんすか? 化け物すか?」
さっきも3回はイッたはずなのに、なんなんだこの男は。
「それだけ愛されてるって事だから、少しは喜べ、神崎」
「はあ? 訳わかんねっ……」
その言葉は咬みつくようにされたキスにふさがれる。
壊れる……このままじゃ、俺は……。この人に蝕まれて、壊れてしまう……。そう頭では思いながらも、俺の身体は馬鹿みたいに反応してしまう。課長の長い指が俺を蹂躙し、そしてどんどん侵略してくる。身体も、心も……。
俺は悔し紛れに、課長の背中に思いっきり爪を立てた。
|
|
|