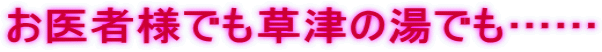結局風呂場でもさんざん課長にもてあそばれた俺は、泊まっていけという悪魔の囁きを振り払い、フラフラになりながら始発に乗った。腰やら膝がガクガクだし、下半身の違和感は尋常ではない。喘ぎまくって喉も嗄れている。はたから見ればまるで病人のような重い足取りで車両に乗り込んだ。いつものラッシュからは考えられないぐらい乗客はまばらだが、その方が座れるだけありがたい。ドアのすぐ傍の座席に落ち着くと、手すりにだるい身体を預ける。
課長の家と俺の家は同じ路線だ。乗り換えなしで帰れるのは幸運なのか。いや、それを口実に毎度毎度課長の家に連れ込まれるのだから、不幸なのかもしれない。たった4、5駅の道のりがやけに長く感じられる。しかも、揺れが直に下半身に伝わってきて、治まりかけた鈍痛がぶり返す。
「……ちっ、何やってんだ、俺……」
最寄駅に着き、重たい身体を引きずるようにして歩くこと10分弱、家にたどり着いた頃には、既に新聞も届き、朝のニュースが始まっている時間だった。
8時前には家を出ないといけないから、1時間も寝られればいい方か。俺は崩れるようにスプリングの硬い安物のベッドに倒れこんだ。
――プルルルル、プルルルル……
耳障りな甲高い電子音が俺の泥のような眠りを妨げた。はっとしてベッドサイドの時計を見ると、針は8時30分を少し回っていた。会社の就業時刻は9時だがいつもなら既に席に着いている時間だ。やばい、遅刻だ!
充電器にもセットせずテーブルの上に転がった携帯はまだ鳴り続けている。急いでそれを手に取った俺は、表示を見て心臓が止まりそうになった。
『高瀬課長』
……マジかよ。俺は怒鳴られるのを覚悟して電話に出た。
「……はい、神崎です」
「神崎。お前今日は午後から出勤しろ」
「はい?」
「この前、ゆかりが早退してお前半日休出しただろ。それの代休だ。ゆかりも今日から戻って来たし」
「え? か、課長……でも」
「いいか、午前中に出てきたらぶっ飛ばすぞ。わかったな。じゃあな」
「――ちょ、ちょっと、課長っ!」
俺の返事を聞きもせずに、一方的に電話は切れた。まったくもう。鬼なのか仏なのか、人でなしなのか優しいのか。こういう事を誰に対してもスマートにやってのけるから、あの口の悪さも我慢できてしまう。飴と鞭の使い方が上手いというのか……。
いや、待て。俺が確実に遅刻する原因を作ったのは結局あの人で。しかも、張本人はごく普通に出勤している。つっこむ側のあの人と、つっこまれる側の俺では体力の消耗度合が違うから当然といえば当然なのだが、なんだか理不尽で腹が立ってくる。
俺はむかつく心を抑えられずに、ぶつぶつと課長への悪態をつきながら携帯のアラームを10時45分にセットした。頭にきた、12時になった瞬間に会社に入ってやる。そう決心してもう一度ベッドにもぐりこんだ。眠りに落ちるのにそう時間はかからなかった。
☆ ☆ ☆
「おはようございまぁーす!」
12時ジャストに『事務所』に入ってきた俺に、案の定課長はデスクから苦い顔で視線を送ってきた。ふっふっふ。こんなことでしか抵抗できないが、でもあの人のあんな顔を見れて、ちょっといい気分だ。
「あ、神崎さん、おはようございま〜す」
課長以外で唯一事務所にいた営業企画部の面々は、挨拶してきたゆかりちゃんだけだった。佐藤ゆかり、23歳。決して美人という訳ではないが、でもその明るい笑顔と人懐っこい性格は周囲を和ませるものがある。事務所組の最年少だ。
「おはよう、ゆかりちゃん。もう大丈夫?」
「はぁい、もう元気バリバリですぅ! いやぁ、急性胃腸炎ってしんどいですね。上からも下からも出るわ出るわで、もう死ぬかと思いましたよ」
「……ゆかりちゃん……」
素直というか何というか。ゆかりちゃんの発言に俺は苦笑いを返すしかない。
「あはは、やだぁ、あたしったら。神崎さんにもご迷惑おかけいたしました」
ぺこりと頭を下げる彼女は、ちょっと照れたように笑った。どうせ部署内恋愛するんだったら、こういうかわいい女の子としたかった……俺は心の中でため息をつく。
「じゃ、ランチ行ってきま〜す」
そう言うと、ゆかりちゃんは管理部の進藤さんと楽しくお喋りしながら事務所を出て行った。病み上がりだというのに元気だ。いつも女子のパワーには圧倒される。うちの会社も数年前までは男性中心だったらしいが、今や店舗のトップの半数は女性社員だし、飲食という仕事柄アルバイトは圧倒的に女性が多い、俺は二人の後姿を見送りながら自分の席に着いた。
「神崎」
案の定、課長が俺の名を呼ぶ。ちらりと目を向けると、まるで日本史の教科書で見た金剛力士像のような表情で課長が俺を見ていた。まったく、いい男なんだから、そんな顔すんなってぇの。
「はい、課長、なんでしょう?」
俺はピカピカの完璧な笑顔を高瀬課長に向ける。それが完全なる作り物である事を熟知しているこの人は、俺の120点の笑顔を見て、ますます仏頂面になる。
「俺は午後から出て来い、そう言ったはずだが?」
「ええ。だから、午後12時きっかりに来ましたよ」
そう言いながら俺は鞄からファイルを取り出す。もちろん顔には営業スマイル。課長の舌打ちが聞こえた。
「そんなに俺に会いたかったのか?」
事務所に残っていた管理部の新田部長や経理部の永沢主任もランチのために出て行き、二人きりになった途端、またもやこの自信過剰男の口からそんな言葉が飛び出して、俺はわざとらしく大きなため息をついた。
「違いますよ。どこの誰ですか、俺に東海物産と鈴木食品の原価比較リスト今日の15時まで提出しろ、って言った鬼課長は」
「はは、そうだっけな」
そう言って笑うと、高瀬課長はスーツのポケットから煙草を取り出し火をつけた。事務所内は禁煙なはずなのだが、就業前後や休憩中に課長が煙草を吸っても上司は誰も咎めない。それだけやる事やって評価されてるからだろうけど。俺だったら見つかった時点で始末書ものだろう。
「……ったく、俺の平凡な能力をあなたと一緒にしないで下さい」
ぶつぶつ言いながらPCの電源を入れた俺は、鞄から買ってきた昼食を出そうと下を向いた時だった。
「そうか? お前のベッドでの能力は十分非凡だぞ」
不意に耳元で囁かれ、ぞくりとする。やや低めで伸びのある課長の声。やばい、耳元でのこの声は反則すぎる。
「――っ! やめて下さい、何考えてんすか? 真っ昼間っから! しかも、ここどこだと思ってんすか?!」
「ふふ、かわいいなぁ、お前はほんと」
自分でも耳まで真っ赤になっているのがわかる。近づいてきた課長の顔を押しのけた俺の手をつかんで、あろうことか、この人は俺の掌に唇を寄せた。ちゅっ、とわざと音を立てて。
「会社だと思うと、余計に燃えないか?」
「――ばっ――馬っ鹿じゃないすか、あんた!!」
他の上司が聞いたら始末書では済まないくらいの、あり得ないタメ口だったが、課長はさして気にした様子もない。いや逆に面白がっているかのように余裕綽々の笑みを返すこの人が、とても憎たらしい。
「やっぱりかわいいなぁ、お前は。その意地っ張りが、喘ぎながらおねだりする時なんか、最高にたまんないぜ」
そんな事を言って、また恥ずかしげもなく掌にキスする。俺はもう、怒る気も失せて、がっくりと肩を落とした。
こんな事なら、13時に来ればよかった、そう思う。しかし、1時間程度でリストを完成させる自信はなかったし、課長はちょっとした入力ミスさえ許さない人間だから、プリントアウト前の最終チェックも重要だ。そもそも俺の予定の中では、午前中に入念にチェックして提出しようと思っていたのだが、この人のおかげですべてが狂ってしまった。
「……高瀬課長」
「なんだ?」
「手、放していただいていいですか? このままじゃ15時までにリスト提出出来ませんから」
むすっとした顔でそういう俺を見て、課長はふっと笑った。時折見せる少年っぽい笑顔が、また俺の心を揺さぶる。
「神崎、お前、飯は?」
「買ってきましたよ。これならPC打ちながらでも食えますからね」
俺は鞄の中からサンドイッチを取り出した。
「課長は飯食いに行かないんですか?」
「ああ、今日はいい」
「何が今日はですか。いつもじゃないですか。よくそんなんで身体がもちますね」
「お、心配してくれてるのか?」
「ええ。課長がぶっ倒れたら営業企画部は一巻の終わりですからね」
そう言って俺はサンドイッチの袋とカフェオレを、課長めがけて投げ渡した。
「そうだろうと思ってましたよ。いいからそれ食って、おとなしく来週の合同研修の資料でも作ってて下さい」
俺の言葉ももはや上司に対する物言いではなかったが、課長はやっぱり気にするそぶりも見せなかった。
「へいへい。わかりましたよ、神崎君」
サンドイッチを咥えながら席に戻っていった高瀬課長を横目で見ながら、俺はまた知らず盛大なため息をついていた。
|
|
|