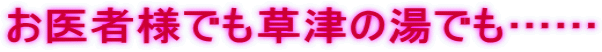待ち合わせ場所の先月オープンしたばかりの居酒屋は、金曜日の夜ともあって満席。予約を入れていて正解だった。この店は元々関西が発祥のチェーン店で、東京進出の2号店だ。うちの会社にとっては今後の大きなライバルにもなりうる。通された席でおしぼりを手で拭きながら、俺は店員の動きを目で追う。しみじみ職業病だな、と苦笑いしつつ俺はメニューに目を通した。
敵情視察を兼ねろ、と指示されたとはいえ、今はプライベートの時間だからあまり仕事の事は考えたくないのが本音だが、最近は気がつくと仕事中心に俺のすべてが回っている。それはもちろん、俺が今この店にいるよう仕向けたあの人のせいでもあり……。
「はぁ……」
「ぷっ。なんてシケた顔してんのよ、カズ」
思わず出た俺のため息に、耳になじんだ女の声が降ってきた。俺はメニューから視線を上げる。店員に案内されて、約束の時間ちょうどに待ち人は現れた。パンツスーツに身を包んだショートボブの細身の女は、やけに気が強そうな瞳が印象的だ。案内したバイト君がちょっと見惚れるぐらいだから、間違いなく美人の部類に入るだろう。ま、俺はこいつの実態を幼い頃から嫌というほど知っているが。
小早川麻里子。俺の腐れ縁、同い年の幼なじみ。
「よ。ただいま」
右手を上げる仕草や言葉使いは、ボーイッシュというより男勝り。しかし、それでも品は悪くならない。こいつの魅力の一つなのかもしれない。
「おう、おかえり。なんかいいもんあったか?」
「もちろん。安価で質のいいの、しこたま仕入れてきたわよ」
そう言ってVサインを出し席に着く麻里子。姉御肌で勝ち気なこいつとは派手なケンカも数えきれないぐらいやらかしたが、次の日にはお互いケロッとしていつも通り、そんな間柄だ。
麻里子はおしぼりを持ってきた店員に有無を言わさずビールを2つ注文すると、俺が持っていたメニューをひったくるように奪った。まったく、こういう所は昔から全然変わっていない。俺は苦笑いしながらマイルドセブン・スーパーライトに火をつけた。
「お前、変わんねぇな、その性格」
「あら、ありがと」
「褒めてねぇよ」
運ばれてきたビールで乾杯する。たった2ヶ月ぶりなのに、こうして麻里子と飲むのがやけに久しぶりのような気がして、ジョッキを置いた俺の口からは知らずまたため息がもれていた。
「はあ。なんかやっぱりお前といると安心するわ」
「おろ? カズったら、20年目の告白?」
「ばーか、んな訳あるか」
「んも~、照れちゃって。素直じゃないんだからっ」
そう言ってにやっと笑う麻里子。いつもの軽口の応酬すら心地よい。
幼稚園から高校までは隣家から同じ学校に通った俺達は、お互いのつきあった相手の顔や期間まで知り尽くしている。大学を卒業し社会人となってからは、流石にお互いに忙しくなり会う機会は減っているが、時々こうやって定例で飲んでいる。俺のよき相談相手であり、ちょっと口うるさい姉貴のような存在だ。正確に言うと俺の方が2ヶ月ほど年上なのだが。
昔から友人を作るのが苦手俺にとって、数少ない信頼のおけるこいつの存在が、今まで何度も俺を助けてくれた……。
「無事に帰って来てよかったよ。南アフリカなんて、かなり物騒だって聞いてたから」
「石のためならこの麻里子様はどこへでも行きますよ。……ま、立石がいてくれるからってのもあるけどね」
唇の端についたビールの泡をぺろりとなめて、麻里子は微笑む。立石というのは、麻里子のお目付け役みたいな人だ。立石慶司、190センチ以上ある鍛えられた肉体の武道の達人だ。多くを語らない立石さんは一歩間違えればその筋の人に見えなくもない。外見はめちゃくちゃ怖いが、実際喋ってみるとそんな事はない、フツーの人だ。まあ、麻里子とうまくやっているんだから、フツーとは言えないかもしれないが。
麻里子はこう見えて実は社長なんかやっている。彼女の親父さんは元々輸入家具屋を営んでいた。2年前親父さんが体調を崩して引退し会社を引き継いだ麻里子は、好きだったパワーストーンやジュエリープロデュースにも手を伸ばし、結構成功している。立石さんが副社長としてしっかり麻里子をサポートしているのも躍進の一因だろう。
「ほんと、立石さんに感謝しろよ。お前一人だったら絶対成功してないからな」
「ま、それは否定しないわ。立石親子には2代で助けられてるからね、うちは」
彼の父親も麻里子の親父さんの腹心だったらしく、今は取締役として彼女の会社に籍を置いているようだ。
「てかさ、このお通し、味濃いね。ここ元々関西じゃなかった?」
「ん? あ、ほんとだ、なんじゃこりゃ」
俺はお通しの切干大根の煮物を一口食べて、思わず顔をしかめた。ここは純和風の居酒屋だし、酒のつまみと考えれば味が濃くなっても仕方がない。とはいえ、うちでこんなもん出したら本並主任に蹴っ飛ばされるレベルだろ……。口直しに2本目の煙草に手を伸ばす。
「で、なんかあった?」
俺の方をまっすぐ見つめてそう言う麻里子。口調は疑問形だが、そのまなざしは確信を持っている時の彼女の瞳だった。
やっぱり。こいつにはわかってしまうんだよなぁ。俺のちょっとした変化も見逃さない。思わず、お前は俺のお母さんか、と思ったが口には出さないでおく。
「……相変わらず単刀直入だよな、お前」
前回麻里子と2人で飲んだのは、俺と高瀬課長がそうなる直前の事だったから、しばらく会わない間に起きた俺の一大事をこいつが知るはずはないのだが……。
「あたしが直球じゃない事あったっけ?」
そう言われれば返す言葉がない。もう食う気もなくなったお通しを箸でつつく俺の向かいで、麻里子はおもむろにボタンを押した。慣れ親しんだ「ピンポーン♪」の音に、つい条件反射で「お伺いいたします」と出そうになる。飲食の世界に戻って来たとはいえ、現場から離れて長いのに……。俺はそんな自分自身に苦笑する。
「はぁい、お伺いしまぁす」
やってきたのは≪あゆみ♡≫とデカデカと書かれたネームをつけた二十歳そこそこのばっちりメイクの店員だ。ちょっと舌足らずで、小首を傾げながら麻里子のオーダーを聞いている。俺は個人的にこういう店員は好きじゃないんだが、男性客受けは悪くないんだろうなぁ、と思う。それにしても、つけまつげばっさばさだなぁ。『お前はセサミストリートのスナッフィーか!』なんて思いながら見ていると、彼女はオーダーを復唱もせずに戻っていった。ちょっと待て!
「あ? なに頼んだ? てか、あゆみちゃん、オーダー復唱しろよ」
「ったく、ぼけーっと辛気臭い顔しちゃって。ま、まず飲め! 2杯目頼んどいたから」
「早っ!!」
俺のジョッキの中身はまだ半分以上残っているというのに、麻里子のジョッキはほぼ空だ。麻里子はザルを超えたワクだから、こいつのペースに合わせたら俺の方が確実につぶれる。しかし、そうわかっていても今日は飲みたい気分だ。酔ってぶちまけてしまいたい衝動に駆られる……。
俺は残っていたビールを思いっきりあおった。
2杯目のビールが届いてしばらくすると、麻里子がオーダーした商品が続々と運ばれてきた。刺身やら揚げだし豆腐やらホッケやら煮込みやら。まるで新橋のサラリーマンの定番のようなメニューのオンパレードに、俺は思わず吹き出す。しかも、麻里子はいつの間にか3杯目もオーダーしていて、しかも冷酒にシフトしていた。当然手酌。
「お前はのんだくれのオヤジかってぇの」
「いーじゃん。久しぶりに帰って来たから日本食に飢えてるの。それに、そんなジョッキ1杯をちまちま飲んでるヘタレ男よりはマシよ」
ちょっと言えば倍以上になって返ってくる。ったく、俺の周りにはこの手の人間しかいないのか、麻里子といい、本並主任といい、あの人といい……。頭を抱えて煙草に火をつけた俺を見て、麻里子はふうとため息をついた。
「疲れてるわね、カズ。会社、合わないの?」
心配そうな瞳を向ける麻里子。本当にこんな時のこいつはお母さんのようだ。言うと怒るから言わないが。
「いや、そんな事ないよ。仕事は充実してるよ。仕事は、ね……」
「じゃ、人間関係?」
「……半分あたりで半分ハズレ」
剥いた枝豆の皮を指でもてあそぶ俺を見る麻里子は、珍しく真剣な表情をしていた。
「はぁ……予感的中かぁ……」
「? 何が?」
麻里子の言葉の意味がわからずに首をかしげる俺。彼女は頬杖をつきながら俺をまっすぐ見つめると、少し思いきったように口を開いた。
「……カズ、あんたさ……」
「お待ったせ致しまっしたぁ~!」
よく言えば威勢のいい、悪く言えば丁寧さのかけらもない茶髪の兄ちゃん≪かとうくん≫が焼き鳥を運んできた。その耳にデカい金ピカのピアスがぶら下がっているのを見て、俺は眉をひそめた。チェーン店とはいえ、いやチェーン店だからこそアピアランスのマニュアルはしっかりしているはずなのだが。店長か、はたまた会社か、どちらにしろ指導がゆるいのは確かなようだ。この店も大した事はないな、と思いつつ、この場に高瀬課長がいたら、
「そのピアス、耳ごと喰いちぎるぞ!」
とかすごい形相で怒鳴りそうだな――なんて考えて、俺は完全に沈黙した。
なんでだよ……。
頭から追い出そうとすればするほど、気がつくとあの人の事ばかり考えている。俺は無意識で、ぷぎゅ、とか訳のわからん擬音を発しながら、テーブルに突っ伏した。
「あれま。これは、相当重症のようで……」
半ばわかっていたような様子で、麻里子はまたため息を吐いた。冷酒のお猪口を置いて、ラーク・ミント・スプラッシュに火をつけたその唇から放たれた言葉に、俺は絶句する。
「ねえ。あんたのその悩みの原因って、高瀬先輩でしょう?」
あまりの言葉に顔を上げ、麻里子の顔をまじまじと見つめた俺。その表情がよほどマヌケだったのか、麻里子はからからと声をあげて笑った。
「ほんと、あんたって懐に入れた人間には素直よね」
「……うるせぇ」
まあ、兄弟同然のこいつだから仕方がないか。俺の、麻里子に言わせれば『史上最強の逆ツンデレ』は、生来のものではない。思春期以降に起きた様々な事件が影響し、常に俺の背中には巨大な猫がいて、顔には完璧な笑顔が貼りついている。その『営業スマイル』を剥がす事が出来て、かつ俺の真の姿を知る人物は数少ない。
「ふふ。あんたの、その一筋縄じゃいかない感じがたまんないんだと思うよ、高瀬先輩には」
「――は??」
思考停止。
麻里子の言葉の意味がまったく理解出来ない。
「なに、気付いてなかった?」
「……な、にが?」
向かいに座る麻里子の満面の笑み。聞きたいような、聞きたくないような……。
「高校の時、なにかっていうとあんたにちょっかい出してたのって、あの人流の愛情表現だと思ってたけどな」
「は?」
意味不明。
「ほら、小学生の男子が、好きな女の子ほどいじめたくなる、ってやつ? あんなの」
「……お前の言ってる言葉の意味が、ぜんっぜんまったくわかんねぇんだけど」
眉間に皺が寄っているであろう俺の顔を見ながら、麻里子はまたからからと笑いながら冷酒をあおった。
「だ・か・ら。……高瀬先輩、カズの事かなり気に入ってたと思うよ。後輩としても、そういう対象の相手としても、ね。まあ、高校時代は一線は越えずに踏みとどまったって感じ」
「……んな訳ねぇって……」
ははは、と乾いた笑いをこぼした俺に、真剣な目を向けてくる麻里子。こういう時のこいつは、やけに説得力がある。
「……っ、だって、じゃあ、あの時の事はっ!!」
思わず声を荒らげた俺に、隣のテーブルの客がちらりと目を向けた。
だめだ、冷静になれ。あの人が絡むと、俺はおかしくなる……。俺は残っていたビールを飲み干すと、通りががった店員の背中にジントニックを頼んだ。
「……う~ん。ま、時効だから言うけどさ。あれ、高瀬先輩が悪いんじゃないよ」
「――っ!?」
ぽつりとつぶやいた麻里子の言葉に、俺はまた絶句する。
「あれ、仕組まれた事なんだよね」
――?! ちょっと待て、そんなの初耳だぞ!
高校時代、高瀬さんはいい意味でも悪い意味でも校内で目立つ存在だった。女子からは興味と好意の視線を、男子からは羨望だけでなく敵意の視線を集めていた。そんな高瀬さんとつるんでいた俺も、結果的には目立っていたんだろう。とある盗難事件の濡れ衣を着せられそうになった事があった。その時、俺と高瀬さんはちょっとした事からケンカをしていて、俺の名を教師にチクったのが高瀬さんだった、はずなのだが……。
「真島先輩っていたじゃん、あいつが仕組んだの」
「真島先輩って、副会長だった? だって、あの人、高瀬さんと仲良かったはず……」
麻里子は肩をすくめて首を横に振った。
「表向きはね。でも、あいつかなり高瀬先輩に嫉妬してたみたい。で、あんたとつるんでるの知ってて、わざと嘘の噂流したのよ。犯人があんたで、チクったのが高瀬先輩だ、ってね」
「……なんで、そんな事」
「さあ? あたしは真島じゃないからあいつの真意はわかんないけど、とにかくあんたを攻めれば高瀬先輩の弱点を突ける、って発想だけは間違ってはいなかった訳で。まあ、腐っても成績トップクラスの副会長だからね、悪知恵も働いた訳ね」
「……う、そだろ……」
ちょうどいいタイミングで≪かとうくん≫が持ってきたジントニックをひったくるようにして、俺は喉に流し込む。ステアしすぎで炭酸が抜けてる。へたくそ! チェーン店の居酒屋とはいえ、こんなもん出すな!
ジントニックのグラスを睨む俺を見つめながら、麻里子はちょっと複雑そうな目をして俺を見つめて笑った。
「あんたの疑いが晴れた次の日、高瀬先輩がいかにもケンカしました、って顔して登校したでしょ? あれ、真島をボッコボコにしたらしいよ。これ以上、あんたになんかしたらタダじゃ済まさない、って」
あの時のあの人の顔が脳裏によみがえる。まっすぐ睨みつけ、そして「見損なった」と言い放った俺に、一言も弁解せずに頭を下げ、寂しそうな顔で笑ったあの顔が……。それ以来、俺はあの人の笑顔を見なくなった。
「……嘘。じゃあ、なんで……」
麻里子はふうと紫煙を吐きだした。まるで今まで黙っていた肩の荷が下りたような様子で、俺を見つめる。
「あの人もあの顔だし、男も女も引く手あまたって感じだったらしいね。あの後あたりからさんざん遊んでたみたい。噂はいろいろ聞いてたよ」
「知らねぇよ、そんな事……」
聞きたくない、そんな事は。俺が知りたいのは、そんな事じゃなくて。
「あたしがあんたの耳に入らないようにしてたもん。ま、20代も半ば過ぎてそろそろ落ち着くかどうかの塩梅の時期に、あんたが転職してきたって訳か……」
麻里子はニヤニヤしながら最後に残ったマグロの刺身を口に放り込む。
「うわ、きたぁ~。わさび付け過ぎたっ、くぅ~」
渋い顔で眉間を押さえる麻里子。
「……お前の言ってる意味が、全然わかんねぇよ……」
思わずぽつりとこぼした俺の言葉を麻里子は聞き逃すはずもなく。
「据え膳食わぬは男の恥? ん、なんか違うな。千載一遇のチャンス? 焼け木杭に火がつく? 飛んで火に入るなんとやら?」
「だから! 言ってる意味がわかんねぇって!」
また声を荒らげた俺を、麻里子は諭すような冷静な表情で見つめてこう言った。
「……だから、あの人は……高瀬昂は昔からあんたに、神崎和仁にベタ惚れだって事! これでわかった?」
「…………」
「カズ?」
「……う、そ、だろ……」
それから先の言葉が出てこなくて、俺は再び完全に沈黙した。
「なぁ~んだ、とうとう食われたか。ま、遅かれ早かれこうなると思ってたけど。で、どうなの?」
「は?」
「ご感想は?」
「――っ! 麻里子っ!!」
真っ赤になって吠えた俺を見て、麻里子はにやりと笑った。後で本人に聞いた所によると、これはつぶしていろいろ白状させてやると思ったらしい。まったく酷いやつだ。麻里子らしいといえばらしいが。そして、麻里子にぶちまけた事で、俺の心も少し楽になった事は否めない。
「かと~くぅ~ん! 冷酒おかわりぃ! あと、お猪口もう1個ね~」
「へい、よろこんでぇ~」
やたら嬉しそうに麻里子は冷酒を追加した。
|
|
|